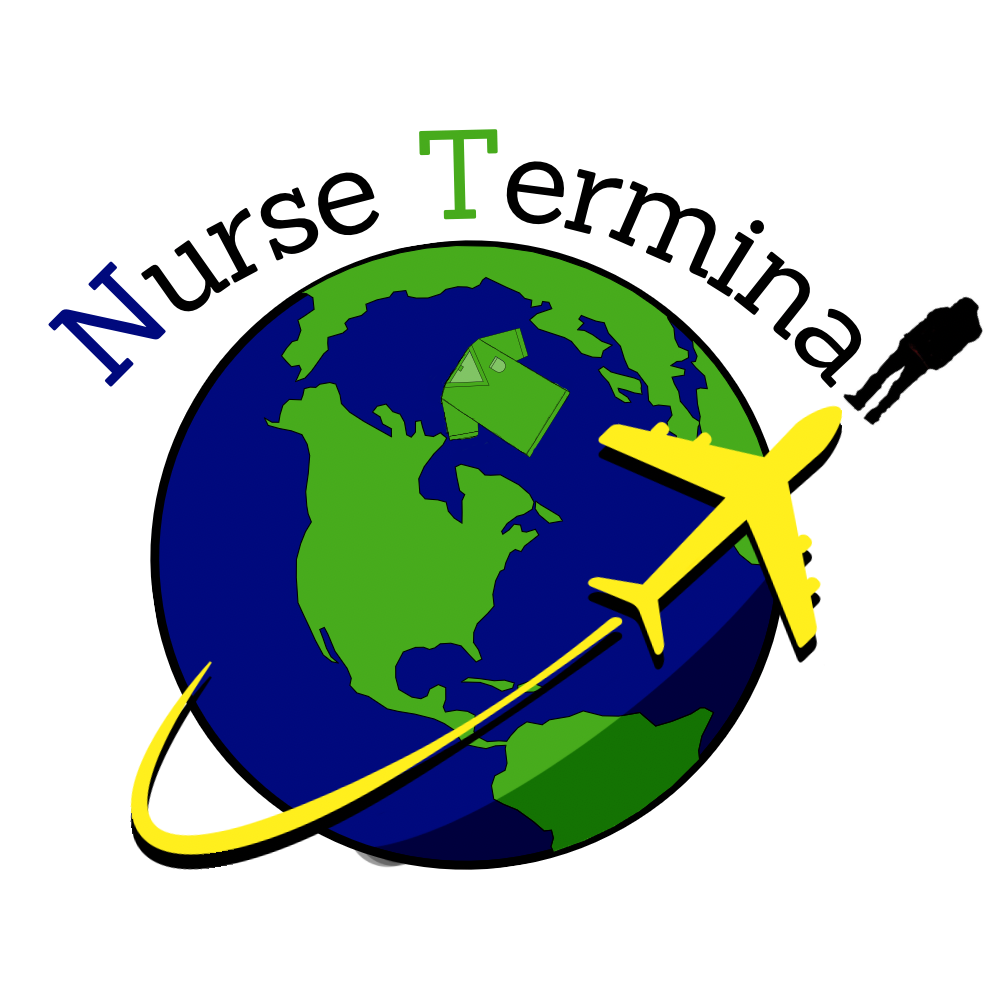「国際看護師に憧れるけど、何から始めればいいか分からない…」
「単位取得や実習、国家試験に向けて勉強で手一杯で将来のことを考えられない…」
かつての私も、皆さんと同じように悩み、そしてたくさんの「後悔」を抱えた一人の看護学生でした。この記事では、ジョンズホプキンス公衆衛生大学院 修士課程に所属する私が、後悔をバネに、どんな行動を起こし、そこからどんな学びを得たか、そして今どんな未来を見ているのか、私のリアルな道のりをお話しします。
この記事を読んだ方が、少しでも世界との距離を近く感じてもらえることができたらいいなと思います!
後悔から学ぶ、国際看護師を目指す学生が今すぐやるべき3つのこと
現役の看護学生さんは毎日、課題に追われててんてこ舞いなのかなと思います笑
日々、授業や演習、実習の準備と大変ですよね。当然、看護学を学んでいるのは、看護師になるためだと思います!
私も少し昔は学部生として、皆さんと同じように「めんどくさい」「大変だな」「なんか実習経験して、看護師ってめっちゃ大変な仕事なんじゃない!?」と薄っすら思いながらも、看護師になるための勉強に向き合っていた時期がありました。
そんな中でした選択は、間違いではなかったと感じています。
しかし、「学生時代にこうしておけば、もっと視野が広がったはずだ」と気づかされることも少なくありません!
そんな話を、私の体験談と共に紹介していきます。
①情報収集をもとにキャリアの選択肢を拡げる
実は私は「就職するなら、まずは急性期病院がいいだろう」という考えで就職先を決め、後悔した経験があります。
その経験から、今では「自分自身のキャリアを、もっと幅広い視点で考えておけばよかった」と感じています。
看護学部は専門学校の要素も強く、看護師国家試験を受験するための学びを中心にされています。そうなってくると「就職は病院かなー」「はじめは経験を積むために急性期を経験した方がいいのかなー」と漠然と考える人が多いのも当然です。
私がお伝えしたいのは、あなたの将来の選択は、あなた自身の人生の目的ややりたいことと一致しているかを考えてほしいということです。
詳細は省きますが、私は最初に急性期病院への就職を選択し、後悔しました。
それは、私がしたいこととはかけ離れていたからです。
だからこそ「企業就職や大学院進学の情報収集」をして「自分自身のキャリアの選択肢を拡げておけばよかった!」と強く感じています。
【Tips】
これまでの経験ですと、国際看護という側面であっても、第一線のみならず。シンクタンクとして上流から国際協力に携われる 国際開発センター なんかもありますし、修士課程を取得した後JPO経由で国際機関に配属を目指すという選択肢もありますね。
これらは、基本的に看護から少し離れた目線での仕事かもしれません。また他にも、卒業後すぐに、国内外の保健学、公衆衛生分野への進学も選択肢としてありますね。私が修士課程でお世話になった神戸大学では、国際協力研究科という国際協力を学ぶ分野があります。
また、看護分野においても、自分の興味関心があれば、国内でも多くの大学院の選択肢があります。また、就職などは考えていないけどという方にとっても、 JICAのウェブサイト にて、国際協力に関連したインターンや求人などがありますので、参考にされたらいいのかなと思います。
②「外の世界」に目を向け、いろんな働き方を知る
2つ目の後悔はもっと外に出ておけばよかったということです。
私は学生時代、もっともっと外でいろんな人と関わりを持っておけばよかったなと後悔しています。
※危ないところには近づかない!
その大きなメリットは、情報を得られることだけでなく、コンプライアンスのしっかりした働き方の基準を知ることができるということです。
正直、看護業界には、働き方のコンプライアンスはほとんどなく、サービス残業やハラスメントが依然残っている現状です。
私なりに考えると、同一化された環境下で、流動性のない人材活用が原因かなと思います。
私の周りでは、看護師→一般企業 or 一般企業→看護師というキャリアを積まれた方が何人もいますが、口を揃えて話されるのが「看護業界は働き方、働く環境がおかしい、ブラックである」ということです。
自身の身を守るためという事という意味でも、「外の世界」に目を向け、自身の中で適切な働き方の基準を知っておくことは重要となります。
【Tips】
今は、学部生でも様々な機会がありますね。xplaneなど留学希望者の交流サイトや地域でのインターン(例えば、難民支援や障害者の方の支援など)の機会など様々あります!これは、私の興味関心の中での選択肢ですので、他にも皆さん探されるといいのかなと思います。
医療でも国立医療協力局などのオンラインでの勉強会もあります。
でも一番いいのは、学部の先輩にコンタクト取って、話を聞いたりすることなのかなと思います。同窓生として、親切に対応してくれるでしょうし、特に病院で働く方だけでなく、国際的な活動をされている方や会社勤めの方などに話を聞くのもいいでしょう。
③英語や看護の勉強
振り返ってみて、どんなことを学生時代にしておけばよかったのかというと、やはり英語や看護の勉強です!
闇雲に看護の知識を高めるということではなく、国際の分野において求められる専門性の高い知識が必要です。
具体的にどのような分野の知識が求められるか。ヒントは、海外青年協力隊の募集にあります。
例えば、2024年の募集では、保健や助産業務、急性期、慢性期の領域や看護師教育の項目が多くありますね。つまり、このような業務が現場で働くとなった場合に求められる分野ということです。
ただ、私は、自分の心からやりたいと思えることを重要視してほしいと考えているため、そのやりたいことと一致するのであれば、上記の需要から逆算してキャリアを積み上げていくことも良いと考えています。
あと、簡単にですが、国際分野(アカデミア)で求められる試験はTOEFL, IELTSです。TOEICもいいですが、早いうちにこれらの国際的な英語のテストであるTOEFL, IELTSに触れていくことも今後のチャンスを広げるという意味では、重要となってきます。
実際にやってよかったこと:世界の解析度が高まった瞬間
これまで、後悔を含め、なんだか偉そうなことを話してしまいました。
逆にやってよかったことはなんだろうと振り返ると、やっぱり原体験を得ることに尽きるなと思います。
フィリピンでの体験
私は看護学部時代の4年間の内、2回ほど学部主催の海外研修に参加していました。
よくある経験だと思うので、簡単にお話しますが、フィリピンに行った時のことです。
「経済成長著しい」「英語が喋れる」「国民皆保険に取り組んでいる」という事前情報を得ており、地域の厚生局に訪問した際には「地域では、すべての住民が保険に加入している」と時しなり気な顔で役所の人がお話しされていました。
しかし、貧困地域に行って話を聞いてみると、住民登録が全くされていない、住人は医療保険について知らないという現状を知ることになります。
「No one left behind(誰一人取り残さない)」という言葉の理念とは程遠い実態がありました。
また、病院見学では、廊下で多くの患者さんが寝ていました。
現地の看護師さんのお話では、「ベッドが足りていない」とのこと。
この経験から、日本の医療サービスのレベルの高さを知ることができました。
アメリカでの体験
アメリカに行った時にも、同じように理想と現実の違いを学ぶ機会がありました。
老人ホームに行った際に、「アニマルセラピーなど多様な生活環境が整備されている」と説明を受けました。
一方でアメリカでは、高額な治療費が現実問題として存在します。格差が拡がり、老人ホームに入れるほど裕福な人は一握り。
例えば、精神科の薬は、保険適用されなければ、30日で10万円以上の費用が発生します。保険適用されれば4,000円〜10,000円ほどになりますが、保険にみんなが入れるわけではありません。
話は逸れますが、アメリカの病棟は、看護師さんたちがナースステーションでゆっくり話をしたり、コーヒーやお菓子食べたりと、日本とは全く異なった職場環境でした。
日本では、昼休憩に職場の休憩室から離れてはいけない、コンビニや食堂利用禁止、ステーションでの飲水禁止などルールがあることを思い出しました。
この経験を思い出す中で、「この人手不足の状況で今のままの働く環境を続けることになんの意味があるのかなー」と、感じることもあります。
あなただけの「国際看護師」を見つけよう
看護学生であっても、幅広い選択肢があることがおわかりいただけたかなと思います。しかし、どれが”正解”なのでしょうか?残念ながらその答えを提示することはできません!
皆さんの中には、参考書ルートのように、これを終えたら次はこれというふうに道を示してほしいと思われるかもしれません。ですが、私は、皆さん各々が考える「国際看護師」というキャリアを自ら育てていくことが重要であると考えています。
自走していくために大事だなという項目はお伝えしました。英語や看護の勉強、インターンなどなど
その先は、自分自身が人生の目的を定めて、自ら創り出してほしいなと思います!
ナスタミでは、様々なバックグラウンドを持った看護師さんの記事があります。今後もたくさん増えていくと思います!その方々のお話を参考にしながらも、みなさん自身が自身を見つめていかれることを願っています。
まとめ:一歩踏み出そうとしているあなたへ
まだまだ、私も周りの方のお力をかりて成長させていただいている立場です。大きなことは何も言えません。
振り返ってみると、別に大きなことをやろうと思って過ごしてきたわけではありませんでした。ただひたすら、原点となった、看護学部時代の海外研修での経験が原動力となって、がむしゃらに取り組んできました。
皆さんにとって、原点といえる強烈な原体験はありますでしょうか?生涯をかけて取り組みたい事はありますでしょうか?
最後に厳しいことをお伝えすると、待ちの姿勢では何も達成できないということです。少し真面目すぎますが…
今は情報が溢れている時代です。その中で、自ら動き、得た体験や知識から自身の身体が動き出すような強烈な原動力を得られることを願っています。