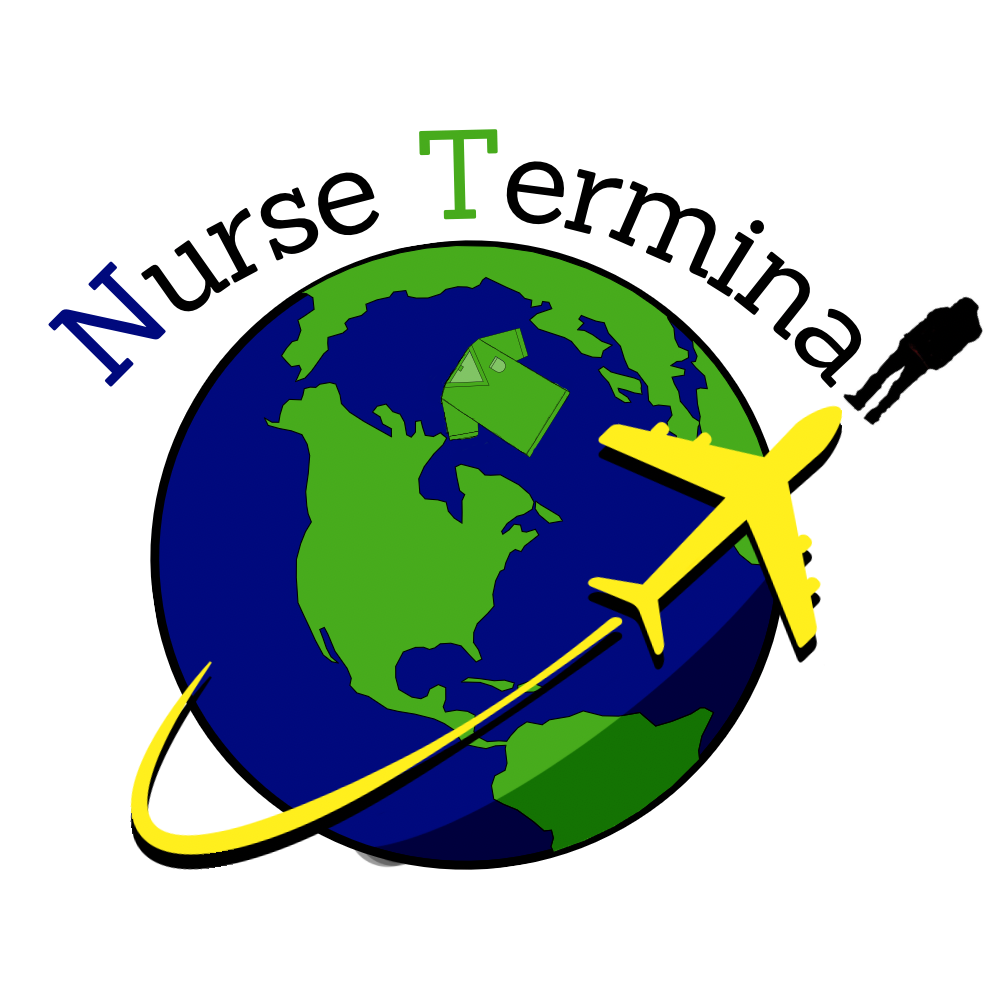Bonjour!じゅんこです。
今回は、転職をしまくっている私から(笑)、私の就職・転職活動について共有しつつ、転職のあれこれについて深堀したいと思います。
実は自分としては、「転職をしている」という自覚がありません。
というのも、私のキャリアの舞台(というとカッコ良すぎるけれど)では、アサインメントやプロジェクトベースで契約を結ぶことも多いから。プロジェクトはいつでも有期です。3年間とか、5年間とか。よって、単純に考えると3年後にはプロジェクトが終わって、自分のポジションもなくなるわけです。そうすると必然的に違う職、ポジションを探す状況に置かれるわけです。
これだけ聞くと過酷ですよね…。そう過酷です。でもこういう業界の中で生き延びている&転職の経験が多いからか、本当にいろんな方から相談を受けます。
それに、日本だと、「転職」っていうとネガティブに捉えられがち?ですよね。
勤続年数が大事だったりするし、転職のときの面接で、なぜ前の仕事を辞めたのか聞かれるのが億劫だったり、自分は一ヶ所で頑張れない人だと思われないかと気になったり。
でも、ずっと同じところにいる必要もないし、この世の人生は一度切りなんだし、やりたいことがあれば挑戦してなんぼ。
昔に比べて「新卒で入職したところに定年になるまで働き続けることを良しとする感覚は少しずつ薄れているのではないでしょうか。私は転職を通して、自分のスキルアップとともに、人生を冒険している感覚があります。
第1章:初めての転職と最初の壁
私が今の業界に足を踏み入れた経緯はこちらのインタビュー記事を読んでいただきたいと思いますが、簡単に言うと、低中所得国での国際母子保健に興味を持ったから。
その前に助産師として臨床での経験を積もうと、新卒で就職したのは大阪の市立病院。
入職した時点から、3年くらいで病院は退職して次の職に就きたいと思っていました。病院にいれば学べることはたくさんあるけれど、「病院で助産師と働くこと」は自分が本当にやりたいこととは違ったので、期間を設定して、その間に学べるものを学ぼう、その後は外に出よう、と考えていました。
最初の転職は、この病院を辞めて、JICA海外協力隊の助産師隊員としてベナン共和国に派遣されたとき。
「住む」ことは「旅行する」ことと大きく異なることを実感しました。そこにある文化、人々の生活など、旅行だと「新鮮で刺激的で非日常的な体験」としてある種、美化されがちなものも、そこに住むことで「自分の日常の一部」になっていく。
ベナンはフランス語圏の国なのでフランス語はもちろん勉強して行きましたが、完璧にコミュニケーションできるレベルにはほど遠く、そして自分が生活していた農村部だと生活言語は現地語。
現地語ができないと買い物も一苦労。インフラ整備も完璧ではないので、停電と断水は日常茶飯事。日本の効率化重視と違って仕事場でもみーんなゆーっくり動きます(笑)クライアントが来ているのにご飯食べたり、まだ業務が残っているのに昼寝を始めたり。仕事への姿勢も違っていて最初はいちいち驚きショックを受けていましたが、日常になっていく。
でももちろん、文化とか考え方ってそのまますんなり受け入れることは難しいことも多いです。最初は日本と比較してしまっていて、「日本だとこうなのに、ベナンだとそうじゃない」とか無意識のうちに優劣をつけてしまっている自分がいました。
とはいえ、例えば妊婦健診で目の前に妊婦さんがいるのに彼女を待たせてまで長々と電話をしている医療従事者の態度は「受け入れる」ことは難しかったです。ここで大事だと気付いたのは、どういう文化か考え方かを「受け入れる=賛同する」必要はなく、あくまでもそれらを「理解する」姿勢が大事だということ。そして勝手に日本のやり方を押し付けてはいけないということ。
もちろん日本のやり方の方がどう考えても効率的で、患者さんにとっても良いサービスを届けられると思うのだけど、その考え方だけが暴走してしまうと、現地を無視してしまうことにつながる。異文化の中で働くって言語だけでなくいろいろな難しさもあるけれど、その難しさをいかに楽しさに変換できるか、そしてそこから自分は何を学ぶのか、そこに醍醐味があるような気がします。
第2章:キャリアの模索と「戦略的」転職の始まり

残念ながらJICA海外協力隊はCOVID-19パンデミックによりベナンから日本に強制送還されてしまいました…2年間ベナンにいる予定だったのに1年間しか居れなかった。不完全燃焼だし、COVID-19なんて保健ど真ん中で自分の専門領域なのにまだ使える人材になり切れてないからこんな状況で返されてしまう。悲しいし悔しかった。
でも、このとき心に決めたことは「もっとデキる人材になって絶対にアフリカに帰ってくる」こと!
これを決心してからの行動は早かったと思います。①リモートワーク可能でアフリカで事業展開しているNGOのインターンを始め、②現場に出られない間にアカデミアのバックグラウンドを伸ばそうと海外院進学を決心し、IELTSのスコアを伸ばすべき死に物狂いでの英語勉強と、③進学資金準備のために2つのパートをかけもちして週6日で働いていました。
この①と③を「転職」に含めるかどうかは人によると思いますが、個人的には立派な転職だったと思います。
①に関しては、やはりアフリカから離れていた当時、自分のモチベーションを保つためにも、且つ情報収集の観点からもこういうアフリカとつながりのある団体に身に置くことは自分にとって大事だと思ったので戦略的に選んでいたと思います。
③については、2つのパートのうち一つは思春期保健に関する仕事で、これはその後の私のキャリアにおいて大きく影響しました。
②の挑戦も幸いにも功を奏し、イギリスの大学院に進学し、無事公衆衛生学修了後は、WHOザンビア事務所で働くことになりました。
ただこのポジションも1年間だったので、1年後には次の職を探す機会がやってきました。WHOにそのまま残るかどうか上司とも相談しつつ、自分としてはJICA海外協力隊のときに関わった地域保健やコミュニティレベルで住民とともに働くことにもまだ関心があったので、NGOに就職することにしました。NGOではアフリカ某国に滞在し、思春期保健に関するプロジェクトを担当しました。
第3章:転職の成功と失敗

転職して「あれ、思っていたのと違った…」みたいな経験はめちゃくちゃあります。
事前に情報収集してなかったの?自分の準備・分析不足じゃない?って言われることもあります。
でも、入ってみないとわからないことってあると思うんですよね。それもそれで経験(という一言で片付けてはいけませんが)。
WHOに入ったときはナショナルレベルの仕事、政策に関わる仕事ができることは嬉しかった一方、やっぱりコミュニティレベルの活動が懐かしくなったのは数知れず。
NGOでの仕事は、滞在国も仕事内容も満足だったけれど、やはりお給料や福利厚生がネックになりました。これは入職前から知っていた事実で自分もそれを了承したけれど、働いてみると、思っていたよりこれらが気になってしまい、自分にとって働く国・仕事内容と同じくらいに福利厚生の手厚さは大事なんだと、自分を再認識する機会にもなりました。
このときに、公私ともにストレスが溜まってしまい、体調を崩してしまったこともあり、契約期間終了とともにNGOから離れることにしました。
幸い、次の転職活動も上手くいき、現在はJICAで働いていますが、滞在国がパキスタンで、日々アフリカロス(笑)。アジアでの勤務経験もあると、自分の知見も今後の選択肢も広がると思っていましたが、やっぱりアフリカの雰囲気好きだったな~と。これも来てみたからこその発見かもしれません。
でも、これらすべてのキャリアから学びを得ています。
WHOでは、政府機関の人々と働く機会が多くあり、彼らとのコミュニケーションや交渉力など鍛えられました。また、日本では経験できないコレラのアウトブレイク対応やポリオワクチンキャンペーンなどにも関わることができたのは、良い経験になりました。
NGOではプロジェクト担当となると、自分の専門性を活かす以外に、バックオフィス業務、経理など全てのマネジメントを任されました。当時は大変だったけれど、この経験を通して、バックオフィス業務を学ぶとともにその大切さを知り、今の仕事にも活かすことができています。
ただ、全体を通して私が恵まれているなあと思うのは人間関係。一緒に働く人たちには本当に恵まれています。この人と相性が合わないから、パワハラにあったから、というネガティブな理由で転職に至ったものは一つもありません。
おわりに
転職をしつつも、自分の根底にある「低中所得国でリプロダクティブヘルス・母子保健に関わること」という軸は変わっていません。
また、コミュニティレベルからナショナルレベルまで幅広い層での業務経験、国連のような多国間援助機関とJICAのようなニ国間援助機関のどちらでも勤務する機会が得られたことは、私にとってとても貴重です。これは、そのときどきで転職という橋をわたってきたからこそ得られたものだと思います。
後編では、いかに転職活動を実りあるものにするか、私の経験から導き出した『キャリアを最大化するための具体的な転職戦略』をお伝えします!