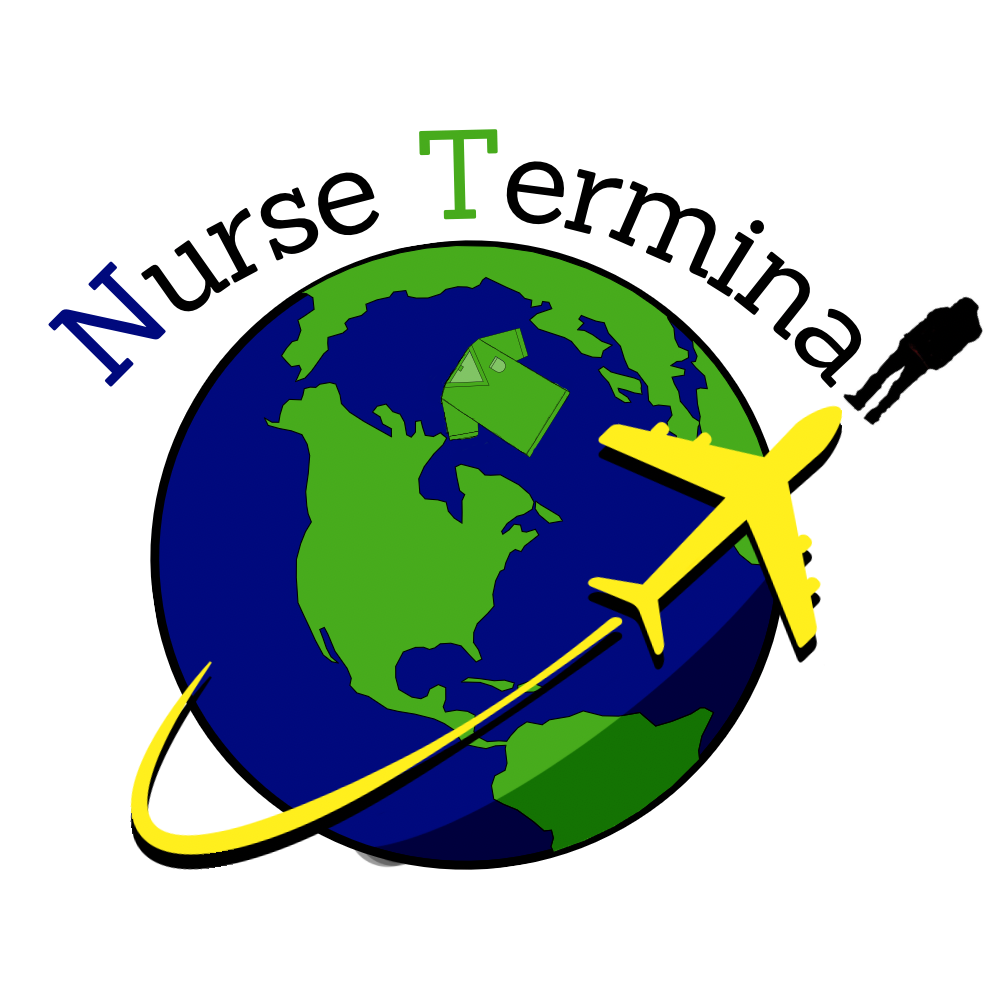<第二部>「世界を舞台に母子保健」~初めての海外への挑戦!~
「世界で働きたい!でも、なにから始めればいいか分からない…」
そんな声に応えるべく、ナスタミでは今、世界で活躍している医療者が語る世界でのあれこれを記事で紹介しています。
世界が舞台の助産師!パキスタンで働くじゅんこさんにリアルを聞いてみた!
〜前回までのあらすじ〜
中村哲先生(ペシャワール会)の”人間の基本的ニーズ”に向き合う姿に影響され、“母子保健”というテーマを軸に世界へ挑戦すると決めたじゅんこさん。
「3年で辞めて海外に行きます!」と宣言し、国内での助産師としてのキャリアを歩みながら、病気になった人だけを見るのではなく”ウェルビーイング”を模索し、ついに国際の舞台に立ちました。
そんなじゅんこさんを待っていたのは人生のターニングポイントとなる出会いと経験の数々でした。
ゆるっと楽しく、でも熱い!芯の通ったじゅんこ節には参考になるアイデアがいっぱい。リズミカルな対話から生み出される母子保健の世界を存分にお楽しみください。

今すぐ行きたい!思い立ったら即行動。スリランカで待っていたものとは
ーいよいよ海外の話!初めての国際医療はスリランカだっけ?
そうそう、待ちきれなくて笑。
JICA海外協力隊には応募していたけれど、まだ選考中のときで、受かるかわからないし「私、今、行きたい!!!」って思って。
プロジェクトアブロードというボランティアを提供している団体の公衆衛生ボランティアのプログラムに参加して、1ヶ月だけスリランカに行きました。
東南アジアだと日本から近すぎ、アフリカは遠い。じゃあ真ん中!南アジア!スリランカやろ!ってことでw
ー行動力はんぱない笑 そこで、どんなことをしたの?
スリランカには、助産師と言っても地域助産師と病院助産師の二種類があって、その両方の現場を見せてもらいました。
地域助産師さんに同行して、産後のお母さんたちの退院後フォローの家庭訪問に行ったり、病院助産師の仕事に関してだと病院で帝王切開のケアを見せてもらったり。
あと、産後健診でエジンバラ産後うつスケールを取っていたのを見て、日本と同じことしてるやん!って感動しました。
やってること、やろうとしていることは日本と一緒。でも、出来ること、出来ないことが違うなと感じました。
例えば、話は戻るけど帝王切開後の産婦さんのケアも術後観察ってこんな軽くて良かったっけ?とか。
ケアはされているんだけど、なんか十分じゃないと言うか。それは医療者の質の問題もあるだろうけど、必要物品がそろってないっていう場合もあったり。
ースリランカでの活動中に特に印象に残っていることはある?
スラムに行ったのは衝撃だったかも…
もうね、なんだろうね。水の汚さ。排水がそのまま川になっているんだけど、臭いもすごくて…。
ー生活の中に当たり前に排水の臭いがあるんだね。
そうそう。あと、生活空間。
スラムの中は、狭いスペースに3世帯くらいがギュッとで暮らしていて。でも、一歩スラムを出ると、そこには大都市の風景が広がってる。
ケニアとかフィリピンとかにもそういう風景があるって聞いたことあるけど、「こんな暮らしがあるんだ…」って再確認させられました。
ーじゅんこさんのスリランカ滞在中は、スラムに寝泊まりしてたわけではないんだよね?
現地の家庭でホームステイしてました。週末には観光地に旅行に行ったり、ビーチに行ったり。
スラムを訪問したその日はちょうど金曜日で、その後サファリパークに行ってホテルで美味しいディナーを食べたんだけど…
あれ、今まで食べた中で一番まずく感じたかも。
あんなふうに暮らす人たちがいる一方で、自分はレストランでご飯を食べて週末を楽しんでいる。そのことに罪はないはずなのに違和感があって。
「これでいいのかな?」ってちょっと考えてしまった自分がいたなあ。
ー清潔さの基準とか、生活のスケール感とか…当たり前が揺らいだ瞬間だったのかもね。
私たちの持っているイメージの違いにも気づかされました。
感染症であるマラリアとかデング熱がある一方で、血糖値240とか、血圧200超えのいわゆる生活習慣に起因した慢性疾患を持っている人たちもたっくさんいて。
あぁ、まさに「二重負荷」ってこういうことなんだなって、体感しました。
ーマラリアなどの感染症を中心とする伝統的負荷、生活習慣病などの非感染性疾患新たな負荷、これらが同時に深刻化している状況のことを「二重負荷」っていうよね。
特に後者が強烈だった。
団体が週一で実施している一般住民対象の健診があって、そのお手伝いもした時の話だけど。
血糖値が高すぎて、「採血する前にご飯たべたでしょ?」って聞いても『食べてない!』って言い張るから、「紅茶飲んだでしょ?砂糖たくさん入れて飲んだやろろ??」ってきいたら『うん!』って。
そんなやり取りが多かったかな笑
ー多くの人がイメージしている、スラム=貧困、ガリガリ、低栄養みたいなのと現実は違ったんだね。
スリランカは1ヶ月じゃ全然足りなかった。スリランカに行ったことでいろいろ見えたけど、その国のことを本当に知るには、もっと人々の生活に入り込んで「この人たちの健康行動の背景には、どんな思いや習慣があるんやろ?」という視点が必要だなって強く感じました。
人生のターニングポイント!?「私…スタートラインにすら立っていない」
スリランカで一番衝撃を受けたのって、医療現場や文化の違いはもちろんだけど、
一緒にホームステイしてたオーストリア人のボランティアの子たちだったのかも。
ーほぉー! それは、どうして?
その2人の女の子、英語もドイツ語もペラペラで。私なんか毎日、電子英和辞典を片手に、一生懸命になってたのに…。
日本人は日本語しかしゃべれへん…ってスタートなだけで絶望やんって!!(笑)
ーぜっ、絶望ではないでしょうよっ!!(笑)
まあでも何で標準装備で2か国語持ってないんだろうって苦い思いをすることは、世界のどこかで活動しているとあるあるかもね(苦笑)俺もそう思ったこと何回もあるし。
英語がわからな過ぎて、最初その子たちのこと「オーストラリア人」だって聞き間違えてもいたし、思ってた笑。
「オーストラリア人な、そりゃ英語上手だわな、うんうん」って勝手に納得してたけど、あとで「え、オーストリア!?母国語はドイツ語なの??」って気づいて…笑
ー英語圏の人だと思ってたんだね。
彼女たちは、別にインターナショナルに働くことに興味があるわけでもなくて、大学の単位を取るための一環で来てた。それであの語学レベル。
私はずっと「世界で母子保健!」って掲げてたけど、実はそのスタートラインにすら立ってなかったんだなって、すごく思い知らされた。
他にもいろんな国から来ている子たちがいたけど、スリランカ人スタッフはもちろん、みんなは英語を共通語で意見交換できているのに、私だけ発言ゼロ。
誰かが言ったジョークでみんなは爆笑やのに、言っている意味わからんから同じタイミングで笑えず、ハハハ😅みたいな愛想笑いしかできない。
語学力、コミュニケーション力、自分ぜんぜん足りへんやん…って。
ー世界の標準からみた自分の立ち位置を知ったんだね。
うん。日本にいるとちょっと英語ができれば、すごい人みたいな扱いされるけど、“当たり前に”英語で活動、仕事をすること。世界でみれば、これが普通。
そこに気が付けたことが、今思うと私にとってターニングポイントだったかもしれないなと思います。
言葉って、コミュ力って大事やなって。
「支援ってなんだろう?」JICA海外協力隊・ベナン派遣で見たリアル
ー次は、JICA海外協力隊でベナンだったよね?行く前の準備って?
ぜんぜーーーーん(笑)。
応募の段階では書類選考と面接がありました。面接に関しては、私は最初モロッコを派遣第一希望国にしてて、現地の宗教行事とか文化背景を踏まえた活動計画書を準備したかな。プレゼンもした記憶があります。
ー合格してからは、すぐ現地に派遣?
いや、合格してから派遣前訓練まで5ヶ月か月くらいあった。
派遣前訓練っていうのは、その名の通り派遣前に語学のレッスンがメインなのだけど、そのほか安全管理やボランティアの心得的なことが組み込まれている2ヶ月強くらいのいわゆる合宿みたいなもの。
その訓練が始まるまでに、JICAから「最低限これはやってきてね」みたいなフランス語教材が届いて、自分でも初心者向けの本を買って勉強しました。
それ以外にも、ラジオ講座も聞いてた。あとは、医療物品が少ない環境でのお産ってどういうものなのかを、自分で助産院に連絡を取って、お産に関わらせてもらっていました。
ーベナンに行く前、不安はあった?フランス語での活動とか特に。
全然なかった(笑)。ベナンは第三希望で書いたけど、そもそも「ベナンってどこ?」ってレベルだったから、まず地図で調べた。
でも、知らない国に行ける!アフリカにいける!って、すごくワクワクしてたな。
ー実際、行ってみてベナンはどうだった?
すっごく楽しかった!でも大変だった。
フランス語をすこし勉強したのに、現地では誰も使ってなくて(笑)
みんな現地語。あとは、電気・水とかインフラが本当によく止まる。
水が3日間出なかったとき、近所の男の人たちがバケツで水を運んできてくれて…あれは感動したなあー。
ー優しいなあ…。活動の中で印象に残ってることは?
「こういう外部からの介入の支援って本当に必要?」って何度も考えた。
現地の人たちは、物は少ないけど幸せそうに見えてね。いわゆる支援や開発って、ドナーがいてお金をやたらと出して「貧しい人々を助けてる」「国の発展をサポートしている」って言うけど、本当に助けてるのかな?って。
この業界にいるとよく耳にする”開発”という言葉も、「開発って、何の開発?何に対して?」って疑問が出てきて。
自分の原点となっている 「(自分より)大変な人々のために何かしたい」みたいな夢や理想が、揺らいだ瞬間だった。
ーなるほど。なんのため、誰のための活動なのか、を考えさせられたんだね。
そう。あとは現地の医療スタッフの社会的立場も高すぎて、日本との違いも痛感した。
妊婦健診で、部屋の前に人が何時間も並んでるのに、スタッフはWhatsApp(世界で利用されるメッセージアプリ)いじってて、妊婦さんは診察室に呼ばれてから10分も20分も待たされている。
医療者はこういうことをしても許される、妊婦や患者は我慢して当たり前。
それが普通になってる現場を見て、「ケアってこういうもんなのかな?こうでいいのかな?」って本当に思った。
お産の時にいきめない産婦さんは叱咤されることもあるし、陣痛室で破水した産婦さんへの対応は日本よりも切迫した対応にならないことが多いし。
でも、それがこの国ではよく見られる光景で。
で、それは日本人から見ると確かに「あるべき姿ではない」ような気もするけど、でもその文化の中で生きている人は、これが当たり前であって。
「私は(日本人として)これは良くないと思う」みたいな感覚で向き合うのは本当に正しいんかな?現地の人は本当に困ってるんかな?みたいな疑問はずっとありました。
あとは、外部からのドネーション(寄付)と思われる大量の医療物品が使われずに倉庫に埃にまみれて放置されていたり、地域にはフランス語が読めない女性が多いのに、某NGOが渡した啓発用看板が筆記体のフランス語で書かれていたり。
これじゃあ誰にも理解されてないよなーって思った。
誰が誰のために何のために世界はお金を使ってるんだろう、ってグルグルしてましたね。
ーそういうさまざまな矛盾に気づいたとき、じゅんこさんはどうしたの?
俺の経験上、支援に関わる人って大きく2つのタイプに分かれていく気がするんだよね。
一方は、「支援はいらない」って考える人たち。たとえば「途上国支援」っていう言葉そのものに違和感を感じたり、そういう活動とは距離を取って関わらない生き方を選ぶタイプの人。
もう一方は、「それでも必要な支援はある」って考えるタイプ。本当に必要なものを届けたいと思って活動を続けていく人たち。
私は完全に後者だった。「本当に必要なものを、どう届けるか」を考えていきたい。じゃないと、今もこの現場には立ってないと思うな。
今ごろカフェとかやってたのかも(笑)
ーいや、じゅんこさんはカフェより米農家とか似合いそうだよ(笑)
農業やりたい!麦わら帽子似合うから!オレンジTシャツ着て、首にタオル巻いて(笑)
次回は…じゅんこ、大学院に行く。
【第3部】「じゅんこ、大学院に行く。長崎からイギリスへ」(後日公開)
おわりに
「ナスタミラジオ」でも、じゅんこさんのエピソードを配信中!
Spotify・Apple Podcast・Amazon Musicなどで「ナスタミラジオ」と検索!
耳から聞く国際看護のリアル、通勤やお風呂時間などにもぴったりです!

↓↓じゅんこさんのSpotifyはコチラ↓↓
第70回 国際協力の話題は尽きません。経験のシェアって楽しいですよね。ゲスト:じゅんこさん – ナスタミラジオ | Podcast on Spotify
さらにナスタミでは「国際看護のリアル」を語ってもらう記事をシリーズで届けています。じゅんこさんの続編記事も配信予定。次回もお楽しみに!!
「海外で働いてみたいけど、どこから始めれば?」というあなたのきっかけになるはず!
「国境を超えて、つながる医療」ー 一緒に実現して行きましょう。
ナスタミ✈は、これからも国際看護に関わるみなさんを応援していきます!!